生成aiを企業で導入する際の課題と対策
生成AIを導入する企業が増えている一方、活用を進める上での課題も明らかになってきています。ここでは、その課題と対策をまとめます。
ガイドラインで偽情報や著作権侵害のリスク対策
生成AIには、ハルシネーションと呼ばれる誤った情報が生成されるリスクや、著作権侵害につながるコンテンツを生み出すリスクがあり、生成物をそのまま利用すると思わぬトラブルが発生する恐れがあります。例えば、企業が生成AIによって生まれたコンテンツを利用する際、それが既存のコンテンツと類似していた場合に著作権侵害に該当してしまう可能性があります。
このような事態を防ぐため、生成AI利用にあたってはガイドラインを自社内で作成して生成AI利用時の注意点をまとめ、周知しておくことが重要です。
加えて、近年では生成AIを巡る訴訟事例も増えているため、自社の取り組みがそれに該当しないか判断できるよう、最新情報のキャッチアップも行うとよいでしょう。
情報漏えいにはガイドラインとシステム両面で対策
生成AIに企業の機密情報や個人情報を入力すると、その情報が学習データとして利用され、情報漏えいにつながる恐れがあります。海外では従業員がChatGPTを利用したことで、社外秘のソースコードが流出してしまった事例も発生しています。
このような事態を引き起こさないためにも、社内の機密情報の取り扱いには十分に注意する必要があります。ガイドラインの整備と合わせ、APIの利用やNGワード設定など、システム環境面での漏えい対策も自社でおこないましょう。
課題を明確化して活用推進
生成AIは多様な用途に活用できる反面、自社のビジネスにどのように組み込むべきか、具体的な戦略の立案が難しいという課題があります。ただ生成AIを利用できる環境を整えるだけでは思うように活用が進まず、期待する成果は得られません。社内の業務は多岐にわたるため、どの業務に対して生成AIを活用するとメリットが大きいのかを見極める必要があります。生成AIを効果的な課題解決につなげるためにも、自社の課題を整理し、どの課題に焦点をあてるかを明確にしましょう。
教育体制を整え、生成AI活用の人材育成
生成AIは比較的新しい技術であり、活用できる領域も幅広いため、業務に導入する企業も増えています。しかし、帝国データバンクの調査によると、生成AI活用の懸念や課題について尋ねた質問に対しては、有効回答企業の54.1%が「AI運用の人材・ノウハウ不足」と回答しています。高まる需要に対して生成AIを使いこなせる人材は依然不足しているといえるでしょう。従業員が生成AIの使い方を学べる研修を開催したり、プロンプトが豊富で使いやすい生成AIを導入したりして、生成AIを活用できる環境を整える必要があります。
出典:生成AI活用は17.3%にとどまる 半数以上が人材・ノウハウ不足に懸念
これらの対策を効率的に進めるためには、生成AIに関する専門的な知識・ナレッジが必要です。自社内でのリソース確保が難しい場合には、適宜外部のサービスを利用することも検討しましょう。
Dify導入と活用における注意点と課題
Difyは原則商用利用が可能
LangGenius社が、オープンソースのLLMOps開発プラットフォームとして公開しているDifyは、原則商用利用が認められています。
DifyはApache License 2.0ライセンスに準拠しているため、企業が社内業務に組み込んだり、独自のアプリケーションを開発・公開したりする用途において、法的な制限を受けずに利用することが可能です。
また、商用アプリとして外部に提供するケースでも、基本的には問題ありません。Difyで構築したアプリをエンドユーザーに提供し、収益を得ることも許容されています。
ただし、商用利用といっても、すべてのケースが無条件で認められているわけではなく、追加ライセンスの取得が必要となる場合があります。商用利用ができないケースについては後ほど詳しく解説します。
Difyの料金プランをこちらの記事で詳しく説明していますので併せてご覧ください。
Dify導入と活用における注意点と課題
Dify を導入することで、企業の業務効率化や生産性の向上に役立ちますが、注意点もあります。ここでは、Dify の導入・活用における注意点や、残されている課題について解説しますので、事前に押さえておきましょう。
顧客情報や社内の機密情報の漏えいリスク
Dify を安定的に運用するためには、セキュリティ対策が重要です。企業が所有する顧客情報や、社内の機密情報を Dify に入力する場合、情報漏えいが起きてしまうと重大なトラブルに発展するリスクがあります。
社会的信用を損なう可能性もあるため、暗号化やアクセス制御といった対策を取り入れるとともに、定期的な安全性の監査を行ってセキュリティ性を保持することが重要です。
また、Dify 上のデータの取り扱いにおけるコンプライアンスを徹底し、ガイドラインや安全対策のルールを明確化し、ユーザーに周知しておく必要があります。
商標利用における機能の制限
Dify は、オープンソースプラットフォームですが、商標利用における機能の制限がある点に注意が必要です。具体的には、OSS版の Dify を独自にカスタマイズし、商用サービスとして提供する際などは、「Dify」という名称やロゴは使用できない可能性があります。
ブランド表示や外部公開を前提とするサービス展開を検討する際は、商標ポリシーやライセンス契約について事前に確認することが重要です。
社内の教育体制とシステム浸透の工夫
Dify は、直感的な操作でAIアプリケーション開発ができる点が最大の利点ですが、使いこなすためにはある程度のプロンプト設計やワークフローの理解も必要です。社内で正式に導入する際には、導入目的や用途を明確にした上で、利用者が使いこなせるよう研修やマニュアルの整備を行いましょう。
社内ポータルでの活用事例の共有や、操作方法の動画、FAQの整備などの対策も有用です。また、Dify の存在や使い方が浸透せず放置され、形骸化することを防ぐためにも、文化としての定着支援も検討しましょう。
Difyの商用利用
Difyの商用利用が許可されるケースとして、以下のような使い方が挙げられます。
- 業務効率化を目的として社内システムにDifyを組み込む(社内チャットボット・FAQ自動応答システム)
- 開発段階での技術検証(PoC)やプロトタイプを作成する
- Difyで構築したAIアプリケーションをSaaSやサブスクリプション形式で一般ユーザー向けに販売する
将来的な商用化を視野に入れた開発フェーズでも、現時点で商用的利益を得ていなければ、ライセンス違反には該当しません。この柔軟性は、スタートアップやAI導入を模索する企業にとって、大きなメリットとなります。
商用利用で失敗しないためのライセンス上の注意点
Difyはオープンソースであり、幅広い商用利用が可能ですが、安心してビジネスに活用するためにはライセンス上のルールを正しく理解しておくことが不可欠です。
- 原則として許可されている商用利用: 以下のケースでは、特別なライセンス契約なしにDifyを商用目的で利用できます 。
- 社内業務システムへの組み込み: 自社の業務効率化のためにDifyで開発したアプリを社内で利用する。
- 開発したアプリの販売: Difyで開発した特定の機能を持つアプリケーション(例:議事録要約アプリ)を、エンドユーザーに有料で販売する。
- APIキーの販売: Difyで開発したAI機能へのアクセスを提供するAPIキーを有料で販売する。
Difyの商用利用ができない・ライセンスが必要なケースは?
Difyは商用利用を原則認めていますが、すべてのケースが無制限に許可されているわけではありません。以下のようなケースでは、商用利用ができない、もしくはライセンスの取得が必要です。
マルチテナントSaaSを提供する場合
マルチテナントSaaSの提供: Difyの基盤を使い、不特定多数の顧客がそれぞれ自身のアカウントでAIアプリを作成・管理できるようなプラットフォームサービス(例:あなた独自のチャットボットビルダーサービス)を運営すること 。
マルチテナントSaaSとは、一つのシステム上に複数の顧客(テナント)を収容し、それぞれのユーザーが独立した環境で利用できるよう構成されたサービスを指します。
複数の法人や個人ユーザーが同一のDifyベースにログインし、専用のAIアプリケーションやデータを操作できるような構成が該当します。Amazonや楽天のようなECサイトが代表的なマルチテナントシステムです。
このような形態では、Dify本体のシステムやUIコンポーネントが多数の第三者に提供されるため、社内利用や個別アプリケーション提供とは異なります。DifyはこのようなSaaS形式の展開に関して、商用ライセンスの取得が必要になる可能性があると明記しています。
マルチテナント構成は利用形態が複雑化するため、開発内容によってはDify開発元の意図する利用範囲を逸脱してしまうリスクもあります。
一方で、自社内で閉じた利用にとどまるケースや、単一クライアント向けに専用構築されたDifyベースのアプリは該当しないとされています。
そのため、マルチテナントSaaSの構築を検討している場合は、早い段階でDifyビジネスチームへ連絡を取り、ライセンス条件を確認することが重要です。
ロゴおよび著作権情報の削除・変更を行う場合
- ロゴおよび著作権情報の削除・変更: Difyのアプリケーション画面に表示されるDifyのロゴや著作権表示を、自社のブランドロゴに置き換えたり(ホワイトラベル)、削除したりすること 。
Difyはソースコードが公開されており、基本的な改変や再配布は認められています。しかし、以下の行為はライセンス違反となる可能性があります。
Difyの管理画面や起動画面に表示されるロゴを独自のロゴに差し替える
画面下部のクレジット表示を消すような変更を加える
Difyの開発者に対するクレジット表示を維持し、プロジェクトの透明性と信頼性が担保されなければ商用利用はできません。
見た目の変更が小規模であっても、意図せずライセンス違反となるケースもあるため、ロゴや著作権情報の扱いには慎重な判断が求められます。
Difyの商用利用のライセンスを取得する方法
以下は、Difyの商用ライセンス取得に向けた基本的な手順です。
- 利用形態の整理
自社がDifyをどのような形で利用するのか、具体的な用途やユーザー構成を明確にする - 問い合わせ先の確認
Difyの公式GitHubリポジトリまたは公式サイトに記載されている「Business Contact」宛てに連絡する - 連絡内容の記載
利用予定のプロジェクト概要・商用利用の具体的な形態(例:SaaS提供、再販、UIカスタマイズの有無)・想定するユーザー数や月間アクティブ数・自社情報(会社名、担当者、Webサイトなど) - 開発元とのライセンス条件の調整
Difyチームからの返信内容に応じて、必要なライセンスの種類や契約条件について協議する - 運用開始
ライセンス契約が締結された後は、合意内容に基づいてDifyを商用利用できます。契約内容は定期的に見直される可能性があるため、契約後も変更がないか注意して運用を続けましょう。
問い合わせ前の確認・準備事項
Difyの商用ライセンスを取得する際に、開発元に問い合わせたいと考える企業も多いと思いますが、その前にいくつか確認・整理しておくべき事項があります。
最も重要なのは、自社で想定しているDifyの利用形態です。Difyの開発環境や商用利用方法によっては、ライセンス違反になるケースがあるため、以下の点を整理しておきましょう。
- Difyを利用するサービスの概要(例:チャットAI、データ分析支援ツール)
- 対象ユーザー(社内利用のみか、外部ユーザーにも提供するか)
- マルチテナント型かシングルテナント型か
- UIやロゴに対してどの程度のカスタマイズを行うか
- アプリケーションやプラグインの再販予定の有無
- 想定される月間ユーザー数
- ユーザーのアクセス規模
- 導入予定企業数
また、事業としてのスケール感も伝えておく必要があります。以下の情報があると、ライセンスの範囲や費用見積もりの見通しが立ちやすくなります。
更に、DifyのApache License 2.0ライセンスそのものについても、基本的な内容を理解しておくことを推奨します。これにより、どの行為ができて、どの行為が制限される可能性があるかを判断しやすくなります。
問い合わせ前にこれらの情報を整理しておくことで、Difyチームとのスムーズなやり取りが可能となり、ライセンス取得の可否判断も迅速に進めることができます。
Difyを商用利用する際の注意点
Difyを商用利用する際は、以下の点に注意が必要です。
オープンソースライセンスは更新される可能性がある
Difyはオープンソースプロジェクトである以上、将来的にライセンス内容が変更される可能性があります。ユーザー数の増加や商用展開の拡大に伴って、ライセンス体系や条件が見直されることは十分にあり得るでしょう。
- 無料で認められていた機能に制限が加えられる
- 商用利用において有償ライセンスの取得が必須になる
また、オープンソースコミュニティでは「バージョンごとのライセンス変更」が行われるケースもあります。そのため、導入時に採用したバージョンのライセンスと、今後アップデートを適用する際のライセンスが一致するとは限りません。
ライセンスの変更は、既存のサービスや開発フローに影響を及ぼすため、Difyを基盤としたサービスを運用する企業は、継続的にライセンス情報をチェックする体制を整える必要があります。ライセンス体系が変更した場合は、運用方針との整合性を取ることも重要です。
長期的に安定した商用運用を目指す企業としては、法務部門やシステム管理者と連携しながら、最新のライセンス情報を把握しておくことが必要です。
商用利用が曖昧なグレーケースはDifyビジネスチームに問い合わせる
Difyはオープンソースとして広く公開されている一方で、以下のようなケースでは、商用利用に関する判断が曖昧になりやすい傾向にあります。
- グループ企業内の他事業部や子会社で運用する場合はマルチテナント型と言えるか
- 顧客企業にDifyベースのシステムを開発・提供した場合にコア機能を基にした「再販」とみなされるか
- Difyをプリインストールした専用サーバーをハードウェア(アプライアンス製品)として販売した場合
こうした曖昧なケースで独自に判断を下すのは、ライセンス違反のリスクを伴います。そのため、Difyのビジネスチームに相談し、商用利用の可否やライセンス取得が必要かを確認することが推奨されます。
問い合わせはDifyのGitHubリポジトリや公式サイトから行うことができます。商用展開の規模や仕様が不確定な段階でも、可能な範囲で利用計画を伝えることで、適切な判断が得られやすくなります。
問い合わせを通じて正式な許諾を得ておけば、ライセンス違反の懸念することなく、安心して開発・提供が可能です。自己判断での運用は避け、Difyの方針に沿った形で商用展開を進めるようにしましょう。


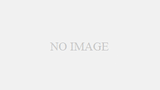
コメント