Dify活用に関するマニュアル・ガイドラインを策定しておく
Difyの商用展開を見据える場合には、社内での運用ルールや技術方針を明文化したマニュアル・ガイドラインを整備しておくことが重要です。
Difyは柔軟なカスタマイズ性や拡張性が特徴である一方で、運用担当者によって、実装方法やライセンスの認識に差が生まれやすい側面もあります。複数人で開発を行う環境や、将来的に他部署・外部パートナーとの連携を想定している場合には、注意が必要です。
ガイドラインを設ける際は、以下の観点を重視しましょう。
- 商用ライセンス取得の基準と申請手順
- Difyの構成変更(UI改変やロゴ差し替え)に関する承認ルール
- アップデート時のライセンスチェックとバージョン管理方法
- プラグイン開発・連携時の注意点と品質基準
- 開発・運用における問い合わせ先や技術的な責任範囲の明確化
これらを整備しておくことで、利用の可否に関する誤解や、ライセンス違反のリスクを未然に防ぐことができます。また、新たにプロジェクトに参加するメンバーに対しても、一貫性のある運用が可能です。
人材の採用
今後は、これまで人が対応してきた作業の多くが生成AIによっておこなわれるようになると考えられています。その時代のなかでもなお求められる人材とは、どのような人材なのでしょうか。
クリエイティビティを発揮する人材
生成AIが普及する時代であっても、人間ならではの独創的な発想や創造力が不要となることはありません。既存の枠組みにとらわれない柔軟な思考を持ち、周囲を巻き込みつつクリエイティビティを発揮できる人材が求められています。
AIを活用し、新たな価値を創出できる人材
AIの特性を理解し、それを活用して新しいビジネスモデルや商品・サービスを生み出せる人材も求められるでしょう。基本的なAIのリテラシーを持ちつつ、新しい技術や活用事例を積極的に学ぶことが必要とされます。
NECでは、AIの”学び”と”実践”の場となるBluStellar Academy for AIを開講しています。BluStellar Academy for AIを活用すれば、生成AIで新しい価値を創出できる人材を育成できるでしょう。
関連サイト:“学び”と“実践”の場を通して社会課題を解決できるAI人材を輩出:BluStellar Academy for AI| NEC

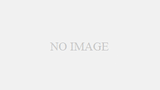
コメント